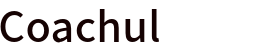適応課題 第1回:仕事を奪われると思ったら、奪われたのは社員のやる気だった!?

適応課題と自走共創をテーマに、今日からシリーズでお伝えしていきます。
〜技術課題と適応課題の違い〜
AIの進化で「やる気レス組織」誕生?
「AIの進化で仕事がなくなる!」と騒がれて久しいですが、経営者として本当に怖いのは、仕事がなくなることじゃなく、社員のやる気がなくなること ではないでしょうか。
最近、企業でこんな現象が起きています。
✔ 業務改善 → AIが提案
✔ 新規事業戦略 → ChatGPTが考案
✔ 顧客対応 → AIチャットボット
✔ 経営戦略 → AIが市場分析
そして、ついに社員が言いました。
「もう、俺ら何したらいいんですか?」
その瞬間、経営者は震え上がる。
「AIの導入は正解だった。でも、この組織…本当に機能してるのか?」
「AIに奪われたのは仕事ではなく、社員のやる気だった」
そんな状況に陥っていませんか?
技術課題はAIが解決する。でも、人の問題は?
AIの進化はすさまじく、「技術課題」はどんどん解決されていきます。
技術課題とは?
✔ 「すでに正解がある問題」
✔ 「ルールや手順を決めれば解決できる問題」
たとえば、
✔ システム導入で業務効率化
✔ RPAで経理業務を自動化
✔ AIでデータ分析し、最適なマーケティング戦略を立案
…これらは、もう人間が頑張らなくてもAIがやってくれます。
では、経営者としての役割は終わったのか?
違います。 ここからが本番です。
なぜなら、AIには解決できない問題があるから。
それが「適応課題」です。
「適応課題」が経営者を悩ませる理由
「適応課題」という言葉、耳慣れないかもしれませんが、あなたの組織にも必ず存在しています。
✔ 「変革の必要性は理解してるけど、誰も動かない」
✔ 「部署間の対立が、もはや文化になっている」
✔ 「上が決めても、現場が全然ついてこない」
✔ 「会議で意見を求めても、シーン…」
これが「適応課題」です。
✔ 技術課題:正解が決まっている(AIやシステムで解決できる)
✔ 適応課題:正解がない(人の意識や行動を変えないと解決できない)
適応課題の解決には、
✔ 人が自ら考え、行動を変えること
✔ 価値観や組織文化の変革
が必要です。
つまり、経営者の仕事はAIが解決できない「適応課題」に向き合うこと。
AIを入れて業務が効率化したのに、組織の雰囲気が悪くなった。
それ、「技術課題だけ解決して、適応課題を放置したせい」 かもしれません。
「適応課題の放置」が招く3つの悲劇
① 変革を促しても、社員が「傍観者」になる
DX推進!組織改革!と掲げても、社員は「またなんか始まったな」と静観。
リーダーがどれだけ旗を振っても、「自分ごと」になっていない限り、人は動きません。
② 部署間の対立が泥沼化する
営業 vs. 経理、マーケ vs. 製造、現場 vs. 本部…
「お前らが動かないせいだ!」と、内部で戦争が勃発 し、結局、誰も動かない。
③ 「とりあえず会議」が増えて、何も決まらない
「意見を聞いて進めよう!」と**「対話」のつもりで会議を開くが、結論が出ない**。
そして気づけば、AIが作った資料を全員で眺めるだけの集まり になっている。
では、どうする?
「適応課題に向き合う方法は?」
それが「対話」と「パーパスの意訳」。
組織が変わるためには、
✔ 社員が「自分ごと」として行動すること
✔ 経営者と現場の「共通言語」をつくること
が不可欠。
つまり、
「なぜやるのか?」を、社員一人ひとりが納得するまで話し合うこと。
「そんなこと言っても、うちの社員、意見言わないし…」
→ それ、対話の仕方が間違ってるかもしれません。
次回は、「対話」が適応課題を解決する理由 を深掘りします!