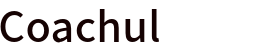適応課題 第2回:『話せばわかる』は幻想だった? 会話で組織は変わらない理由
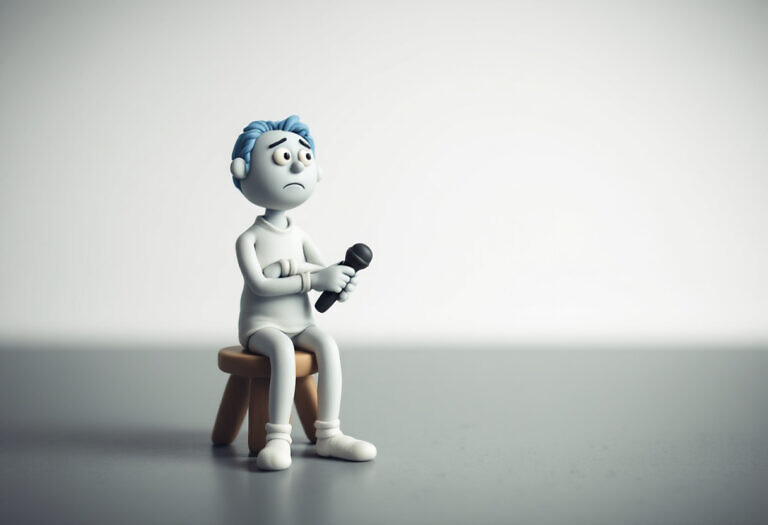
適応課題と自走共創をテーマにシリーズでお伝えしている第2回目。
〜なぜコーチングが必要なのか?〜
会議が増えたのに、何も変わらない現象
「うちの会社、会議ばっかり増えてるんだけど…」
「社員の意見を聞いてるのに、なぜか何も変わらない…」
こんな悩み、ありませんか?
会議室では「貴重なご意見ありがとうございます」と言いながら、会議後の雑談では「また無駄な時間だったな」と愚痴る社員。
意見を聞いてるはずなのに、誰も本気で動かない。
むしろ、「社長が意見を求めると、みんなシーンとする」というサイレント空間 が誕生していませんか?
そう、これが「対話がない組織」の典型 です。
「会話」と「対話」は、まったく別モノ
多くの企業で、「社員の意見を聞く場を増やせば、組織は活性化する」と思われています。
でも、実際は、会議を増やしても、One on Oneをやっても組織は1ミリも変わらないことがほとんど。
なぜなら、会話と対話は違うから。
✔ 会話 = 情報のやり取り
✔ 対話 = 相手の内面を引き出し、思考を変えるプロセス
例えば、こんな会話を想像してください。
上司:「うちの会社、どうすればもっと良くなる?」
部下:「もっと裁量が欲しいですね」
上司:「なるほど!ありがとう!」
(数か月後、何も変わらず)
これ、会話は成立しているけど、何も動かない 典型例。
なぜなら、「裁量が欲しい」と言った部下自身が、どうすればいいか分かっていない から。
経営者がすべきなのは、
「意見を集めること」ではなく、
「対話を通じて、社員が自ら答えを出す場をつくること」 なのです。
「本音を引き出す対話」がないと、組織は硬直化する
日本企業でよくあるのが、「会議では静かに、居酒屋で炎上する」現象。
これは、「対話の欠如」が原因です。
✔ 会議では忖度(上司の顔色をうかがう)
✔ 居酒屋では本音(でも直接は言えない)
こうなると、
✔ 会議は「報告の場」と化し、何も決まらない
✔ 就業後が活性化し、社員が愚痴を言い合う場になる
✔ 社長は「俺の前ではみんな賛成してたのに、なぜ?」と困惑する
結局、「言っても無駄」となり、社員の思考停止が加速する のです。
「対話の力」で、社員の思考を動かせ!
ここで、ある企業の事例を紹介しましょう。
ある中堅メーカーの社長が、社員から「組織の風通しを良くしてほしい」と言われました。
社長は、「じゃあ、どうしたらいいと思う?」と聞きました。
すると社員は、「…いや、それを決めるのは経営じゃないですか?」
…これです。
これが、対話がない会社の典型パターン。
「組織の風通しが悪い」と言うが、自分で変える気はない。
これを放置すると、社員はどんどん「指示待ち人間」になります。
そこで、社長はコーチング的アプローチを試しました。
✔ 「風通しが悪いって、どういう場面で感じる?」
✔ 「もし君が社長だったら、何を変える?」
✔ 「仮に、1つだけ実験的に変えられるとしたら?」
…すると、最初は黙っていた社員が、だんだん話し始めたのです。
そこで、コーチング的問いを使って「社長と1on1の対話会」を実施。
この結果、少しずつ組織に変化が起こり、「意見を言えばちゃんと議論してもらえる」 という空気が生まれました。
「問い」が変わると、社員の行動が変わる
経営者が使うべき問いかけは、
✔ 「どう思う?」ではなく、「どうしたら?」
✔ 「問題は?」ではなく、「どう解決する?」
✔ 「なぜ?」ではなく、「何を?」
こうした問いかけをするだけで、社員の思考が「問題指摘型」から「解決策を考える型」に変わります。
すると、
✔ 「会社が変わるべき」と文句を言うだけだった社員が、自分の行動を変え始める
✔ 部署の対立が、「どうすれば協力できる?」に変わる
✔ 上司への忖度が減り、議論が活発になる
経営者が対話のスタイルを変えるだけで、「社員が自走し、共創する組織」 へと変化するのです。
次回予告:「言ってることとやってること、違いますよね?」
次回は、「適応課題の4つのタイプ」について。
第3回では、「ギャップ型」 を掘り下げます。
「ダイバーシティ推進!」と言ってるのに、幹部は全員おじさん。
「失敗を恐れずチャレンジを!」と言いつつ、失敗したら評価が下がる。
次回も、エグゼクティブコーチングx自走共創の視点で深掘りしていきます!