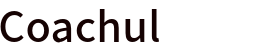適応課題 第5回:撤退が正解? 誰も言わない――抑圧型の怖さ

シリーズでお届けしている「適応課題と自走共創」。5回目はタイプ3「抑圧型」。沈黙は金?いえいえ、沈黙は会社のリスクです。
〜適応課題③:抑圧型〜
沈黙リスク:気づいたときには手遅れ?
会議中はやけに静か。
上司の提案に対して、メンバーはうなずくだけ。
ところが終わってみると、裏チャットや居酒屋では不満や不安が炸裂している――。
こうした光景は、どの組織にも少なからずあるのではないでしょうか。
「言いにくいことを言わない」状態のまま走り続けると、
後になって「もっと早く言ってくれれば…」と痛感する場面が急増します。
これは、抑圧型適応課題が原因かもしれません。
表面上は波風立たない一方、肝心のリスクや撤退案が闇に葬られ、
組織が大きな痛手を負う可能性が高いのです。
A社の事例:オンデマンド印刷が“価値1/2”に
小ロット印刷で注目を浴びたA社。
- コロナ前は「日本人は紙を好むし、ペーパーレスなんて来ない」という空気が支配的。
- 経営陣も「今の事業をずっと続けられるはず」と信じていました。
しかし、コロナ後のテレワーク普及で、紙の需要が一気に減少。
A社の印刷事業の資産価値は、当初見込んでいた金額の1/2ほどにまで下がってしまいました。
実は、早い段階で「今のうちに売却すれば、事業展開できるかも」という声があったようです。
でも、社長や役員に直接そう伝える人は現れず、
会議後の飲み会で「こんなの続けたらいつか破綻するよね…」とぼやくだけ。
結果、A社は完全にタイミングを逃し、時すでに遅し――。
言いにくいことを抱え込む“沈黙リスク”が、まざまざと浮き彫りになりました。
言えずにゆでガエル:抑圧型の落とし穴
抑圧型が厄介なのは、外から見ると平和そうに見えるところです。
- 反対意見がなければ、上司や社長は「皆が賛同してる」と勘違い。
- 実際は、現場が「降格されたら嫌だし…」と萎縮しているだけ。
- 気づいた時は茹でガエル状態。会社の体力や資産価値が損なわれ、身動き取れず・・・。
まさにA社のように、
「こんなの続けたらやばい」とわかっていても誰も動かない。
これこそ、抑圧型適応課題の怖さです。
「パーパス意訳」で沈黙を破る:社長批判にならない仕組み
A社は「想いを残す持続可能な社会を創る」というパーパスを掲げていましたが、
いつしか「想いを残す手段」=「紙」に固く結びつけてしまい、
他の選択肢を考える余地が消えていました。
ここで役立つのが、パーパス意訳です。
- たとえば、「5年後、社会がどう変わるか」を一緒に描く。
- 「私たちの会社が“想いを残す”ために、紙以外の選択肢はないだろうか?」
こうした話し合いなら、社長の個人批判にはならず、
「パーパス実現のため」という大義名分を共有できます。
さらに、エグゼクティブコーチが「そもそも社長の成功体験とは?」と問いかけることで、
トップの思考枠を柔らかくほどくことが期待できるのです。
本音が引き出される理由:“会社×社会”の視点を手にするから
パーパス意訳で重要なのは、個人ではなく“会社の存在意義”を起点にする点です。
- 「社長がダメ」ではなく、「今の社会の変化に合うかどうか」。
- 「トップに逆らう」ではなく、「パーパスに照らすと撤退も選択肢かもしれない」。
こうなると、
沈黙していた声は「会社のための提案」として認められやすくなり、
抑圧型の最大の難所である“言いにくさ”がぐっと下がっていきます。
あなたの会社では、“言いにくいこと”がしっかり議論されていますか?
もし「ウチはみんな賛成してくれるから平和だよ」と思っているなら、
実は裏で「こんなの続けたらやばいよ…」と囁かれているかもしれません。
抑圧型を脱するためにも、パーパスを再確認し、未来の社会と自社の姿を照らし合わせてみてはいかがでしょう。
言葉にならない沈黙が聞こえるようになったとき、
組織は新たな可能性を手にしているはずです。
次回予告:「本質から逃げ続ける回避型――傷口は広がるだけ?」
次回は、適応課題の4つ目にあたる回避型を掘り下げます。
たとえば離職率対策のために「懇親会をやろう」とする会社、
ストレスフルな現場に「研修や福利厚生を足せば解決だ」と思い込み、本質を先送りする現象――。
こうした回避が続くと、いつか大きな歪みが噴出するかもしれません。
“抑圧”が「言いにくいことを言わない」状態なら、
“回避”は「言うべき問題をそもそも別の行動でごまかす」状態とも言えそうです。
果たしてその先に待つものは何なのか。
次回も、エグゼクティブコーチング×自走共創の視点で深掘りしていきます。