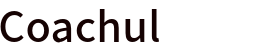適応課題 第6回: 給料を上げてもローカル社員が辞める? それ、回避型の落とし穴です

シリーズでお届けしている「適応課題と自走共創」もいよいよ6回目――今回は回避型について考えていきます。
「本当の問題は別にあるのに、手っ取り早い施策でごまかしていない?」
そんな現象を見かけたら、回避型適応課題かもしれません。
たとえばある国の現地法人。
ローカル社員の離職率が高まり、経営陣は「給料や休暇を増やせば解決!」と大盤振る舞い。
最初は「おっ、気前がいい」と好感触だったものの、数か月後――離職率は相変わらず。
「なぜ?」と頭を抱えているうちに、会社のコストはじわじわ上昇していきます。
1)「待遇さえ良ければ辞めない」は思い込み?
- 幹部ポストは日本人駐在員で固定。
- 会議や意思決定も日本語メイン。
- ローカル社員は現場作業だけでキャリアアップが見えない。
給与を少し上げても、未来が開けないなら転職しよう――
ある情報では、そんな気配が漂っています。
本当の原因は**「幹部になる道が見えない」「言語の壁がある」**などかもしれません。
しかし経営陣は、手間のかかる改革を避け、「簡単にできる待遇アップ」に走る。
いわゆる回避型は、これで失敗を重ねてしまうわけです。
2)なぜ回避する? “痛い改革”を避けたい心理
本当は、社内運営を大きく変えないとローカル社員は定着しないかもしれません。
- 英語(あるいは現地語)で会議する必要がある
- 現地社員を幹部候補に登用し、意思決定プロセスを共有する
- 日本人駐在員も新しいコミュニケーションスキルを磨く
どれも大変そうですよね。
そこで「給料上げときゃOK」と“楽な施策”に逃げてしまう――
これが回避型の特徴です。
問題そのものにはメスを入れず、別のやりやすい方法でごまかしてしまうのです。
3)回避型あるある:“やってる感”だけが先行する
回避型が厄介なのは、「会社として動いているのに成果が出ない」状態を生むこと。
- 「給与アップしました! 年休も増やしました!」とアピール
- 社員から「うーん、根本が違うんだけど…」という反応
- 数か月後、「なぜ離職率が下がらないんだ?」と経営陣がまた混乱
どんなに施策を増やしても、本質に触れていなければズレたまま。
気づけば優秀なローカル社員ほど外資系や他国企業に引き抜かれ、会社の成長力はダウン。
それでも「あれ? 給料上げたのに…」と首をかしげるばかり――
これが回避型の泥沼です。
4)エグゼクティブコーチのシンプル質問:逃げずに考えよう
回避型に陥っている会社ほど、「うすうす分かってるけど面倒」な空気が蔓延。
ここで効いてくるのが、エグゼクティブコーチからの問いかけです。
- 「5年後のあなたが、今のあなたに声をかけるなら?」
- 「ローカル社員の視点で会社を見ると、なぜ辞めようと思うでしょう?」
どちらも「痛い改革」を正面から考えるきっかけを生みます。
言語運営や幹部登用への挑戦を先延ばししてきた社長や駐在員が、
「今は楽でも、数年後には会社の未来が危ういかもしれない」と思い直すかもしれません。
5)パーパス意訳で“5年後の社会”を描く:給料だけじゃムリでしょ?
さらに、パーパス意訳が回避型を抜け出す手助けに。
もしこの企業のパーパスが**「現地と共創し、新しい価値を創る」**だとしたら?
5年後、その国の経済成長や人材市場はもっと成熟しているかもしれません。
- 幹部が日本人だけだったら、現地の視点が取りこぼされる
- 会議が日本語だけだと、現地社員が新しいアイデアを出せない
- 給料アップは一時的な延命策にすぎず、心から「ここで働きたい」と思わせるには不十分
パーパスを意訳し、“この国の未来に自社はどう貢献する?”と考えれば、
「痛い改革から逃げるのはもったいない」と自然に理解できるでしょう。
6)まとめ:楽な道を選ぶほど、問題が積み重なるのが回避型
「手間が少ない施策」で済ませると、
- 離職率は下がらず、
- コストは増え、
- 問題は大きくなるばかり。
一方、英語化や幹部登用などは確かに重労働ですが、
それによってローカル社員のやる気や成長が引き出されれば、会社には大きなプラスになるかもしれません。
楽な道(給料アップ)をとり続けるほど、抜け出しづらくなるのが回避型の怖さ。
でも、痛みを受け入れて本質に向き合えば、未来が一変する可能性もあるはずです。
あなたの現地法人で、待遇改善ばかりに注力していませんか?
もし回避型が蔓延しているなら、根本にある“運営スタイルの変革”を先送りしていないでしょうか。
「痛いから後回し」ではなく、5年後の社会とローカル社員の視点からパーパスを見直せば、
いま踏み込むべき本質的な改革が見えてくるはずです。
次回予告:特別編 ミッション(会社の使命)とパーパス(社会に対する存在意義)の違いと適応課題
これで、「ギャップ型」「対立型」「抑圧型」「回避型」の4タイプをすべて取り上げました。
そこでカギだったのは、エグゼクティブコーチング × パーパス意訳でした。次回は、「適応課題の特別編」として、なぜパーパスなのか。ミッションではダメなのか。どうやって会社が自走共創へと進化していくのかを深掘りします。
お楽しみに!