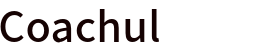適応課題 第7回:Missionでは足りない? Purposeこそが4タイプ解決の鍵

シリーズでお届けしている「適応課題と自走共創」。前回まで適応課題の4タイプを見てきました。今回は、私が経験を通して見出した”ミッションではなくなぜパーパスが必要なのか”を紐解いていきます。
〜適応課題と自走共創メソッド・特別編〜
◆ Mission – Vision – Value(MVV)が壁にぶつかる瞬間
一般的に、企業の方向性を示すとき、
Mission(会社の使命)・Vision(将来像)・Value(価値観)セットがよく使われます。
たとえば「当社は○○という事業ドメインでリーダーを目指す」「××を社会に提供する」など。
一見素晴らしい仕組みに見えますが、適応課題を解決する観点から見ると、
Missionで解決できない壁にぶつかるときがあります。どんな時でしょうか?
(1)M&Aしたら“Mission”が2つ?同じゴールを描けない…
買収されたA社の社員は、「うちはこのMissionで頑張ってきた」と言い、
買ったB社社員は「うちのMissionに従ってもらう」と主張。
両社共に、長年の誠実な取り組み、お客様から選ばれてきた実績、自社のMissionに自負があるからこそ生まれてしまう対立。安易にB社のMissionを採用しようものなら、M&Aが失敗してしまうケースにまで発展する可能性があります。
たとえば、**“対立型適応課題”**の例で考えると分かりやすいです。
部署間の対立どころか、会社間のミッションがぶつかれば、
「自分たちのMissionこそ正義!」という衝突がエスカレートしやすい。
Missionは**“会社”を起点にする**ため、別々の会社が合流すると、
それぞれのMissionがぶつかり合ってしまうんですね。
(2)抑圧型や回避型でも、Missionが枠を狭める?
抑圧型で言えば、
「うちは○○の事業ドメインでNo.1になる」というMissionがあると、
外部環境が大きく変わっても、そのドメインから外に出づらい。
「実はプリント以外の方法で“想いを残す”ほうが現代に合うかも」と思っても、
Missionに印刷ドメインが明記されていたら、それを否定するのはタブーになりがちです。
回避型でも同じ。
Missionが特定領域に縛られていると、企業が「そこから外れた選択」を考えるのが難しくなります。
会社のドメインを崩すことに抵抗があり、本質的な変革から逃げてしまう――
これが回避型の泥沼を深める原因にもなります。
◆ Mission vs. Purpose:視点は“会社”か“社会”か
そこで出てくるのが、**Purpose(社会に対する存在意義)**という考え方。
Missionが「我が社は何をする会社か?」という会社起点の宣言である一方、
Purposeは「社会へどう貢献するか?」という、もっと大きな視座を扱います。
- Mission:うちは○○分野でトップになる!
- Purpose:社会や人々が求める○○を実現するために、私たちはどう在るべきか?
たとえば、“想いを残す持続可能な社会を創る”というPurposeを掲げれば、
仮にプリント事業が時代に合わなくなっても「そもそも何を残したいのか?」と考え直せます。
社会を見たとき、紙のドメインは関係ないのです。紙ではない別の方法に挑戦する柔軟性も生まれますよね。
(1)M&Aで社員同士が敵対していても…
Purposeなら「2社のMissionをどう合わせるか」ではなく、
**「両社とも、社会に向けた目的は何だろう?」という対話が可能です。
相手を否定するのではなく、一緒に“社会のゴール”**を見る形に切り替わる。
部署間や会社間の対立が起きやすいM&Aでも、Purposeが共通言語になれば衝突を和らげやすいわけです。
(2)社長の“枠”を外すにも、Purposeが効く
抑圧型や回避型の事例でよく出た「社長が思い込んでいるMission」を覆すのは至難の業。
でも、**「社会がどう変化しているか」**に目を向ければ、
社長が「…そうか、うちの印刷ドメインだけじゃないのか」と気づきやすくなる。
これは、Missionではなく、Purposeだからこそ実現できるアプローチです。
◆ 結論:Purpose – Vision – Valueが4タイプを超える鍵
Missionを否定するわけではありません。
ただ、適応課題(ギャップ・対立・抑圧・回避)を乗り越えるには、
会社だけの視点に閉じ込もらず、社会という大きなフィールドを見渡す必要があります。
- Missionに閉じると「うちの会社はここ!」と強く意識しすぎるあまり、柔軟な変化を逃しがち
- Purposeなら「社会に向き合う」視点で、新しい道を見つけやすい
Missionが会社の枠を固めるほど、M&A後や事業転換時に衝突が起きやすい――。
逆にPurposeなら、社会という共通ゴールを見られるから、会社が違っても協働しやすい。
プリントのオンデマンド会社が、「想いを残す」Purposeで新たな一歩を踏み出したように、
**“社会視点”**が経営の適応課題を解決へ導く大きな鍵となるでしょう。
Missionを超えて、Purpose – Vision – Valueへ。
その一歩が、組織の未来を大きく変えていくのではないでしょうか。
次回予告:「4タイプ総まとめ。自走共創への道を探る」
これで、「ギャップ型」「対立型」「抑圧型」「回避型」の4タイプをすべて取り上げました。
次回はいよいよ「適応課題と自走共創」の最終回。4タイプを総合しながら、どうやって会社が自走共創へと進化していくのかを深掘りします。
エグゼクティブコーチング × パーパス意訳の視点で、
組織が本当の意味で変わるステップをお届けする予定です。
お楽しみに!